3年に一度実施される特定建築基準適合判定資格者講習があります。講習を受けて、最後の終了考査に合格すると、特定建築基準適合判定資格者として、建築基準法第6条の3第1項ただし書きにある特定構造計算基準に適合するかどうかを審査することができます。
その過去問が日本建築防災協会のHPに掲載されているのですが、解説がないため解答案を作成してみようと思います。
講習の受講案内のリンク 日本建築防災協会HP
特定建築基準適合判定資格者講習|(一財)日本建築防災協会|建築物の防災並びに維持管理制度・技術の調査・研究。資格講習、耐震チェックプログラムの紹介。 (kenchiku-bosai.or.jp)
本ページはプロモーションが含まれています
[広告]
令和2年度 問10
地上4階建ての鉄筋コンクリート造建築物の桁行方向の設計に対して、次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
ここで、各階の固定荷重と積載荷重の和は3,000kN、計算方向に設けた無開口の耐力壁の水平断面積は1m2、構造耐力上主要な部分である柱の水平断面積は3m2、計算方向に設けた、長さが45cm以上で、かつ、開口高さの30%以上のそで壁の水平断面積は1m2、耐力壁以外の鉄筋コンクリート造の壁(上端及び下端が構造耐力上主要な部分に緊結されたもの)で計算方向に設けたものの水平断面積は2m2である。また、コンクリートの設計基準強度は 24N/mm2、地震地域係数Z=1.0である。ただし、1~4階のAiは、それぞれ 1.0、1.1、1.2、1.4とし、√24/18を1.2として計算するものとする。
- 1階はルート2-1の壁量・柱量の規定を満足している。
- 1階はルート2-2の壁量・柱量の規定を満足している。
- 2階はルート2-1の壁量・柱量の規定を満足している。
- 2階はルート2-2の壁量・柱量の規定を満足している。
【過去の考査問題の出典】
出典:令和2年度 特定建築基準適合判定資格者講習 修了考査結果 2.考査問題 から引用していました。現在は、考査問題は公表されておりませんが、結果は公表されております。
解答(案)
解答案は、2
耐力壁以外の鉄筋コンクリート造の壁をAcに入れる入れないを理解しておくことが、解答のポイントになりそうな問題でした。
解説
- Σ2.5αAw+Σ0.7αAc=2.5×1.2×(1×106+1×106)+0.7×1.2×(3×106+2×106)=10,200,000mm2>0.75ZWAi=0.75×(3,000×4F)×1,000×1.0=9,000,000、適切。
- Σ1.8αAw+Σ1.8αAc=1.8×1.2×(1×106+1×106)+1.8×1.2×(3×106)=10,800,000mm2<ZWAi=(3,000×4F)×1,000×1.0=12,000,000、不適切。
- Σ2.5αAw+Σ0.7αAc=2.5×1.2×(1×106+1×106)+0.7×1.2×(3×106+2×106)=10,200,000mm2>0.75ZWAi=0.75×(3,000×3F)×1,000×1.1=7,425,000、適切。
- Σ1.8αAw+Σ1.8αAc=1.8×1.2×(1×106+1×106)+1.8×1.2×(3×106)=10,800,000mm2>ZWAi=(3,000×3F)×1,000×1.1=9,900,000、適切。
最後にルート2主事試験に持ち込み可能な図書の紹介
[広告]
修了考査時に持込可能な図書なので、考査時までに購入しておくのがおすすめです。
これから購入する方は、2025年版が、令和7年7月1日に発売になるので、そちらをご購入ください。

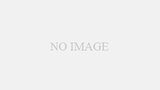
コメント